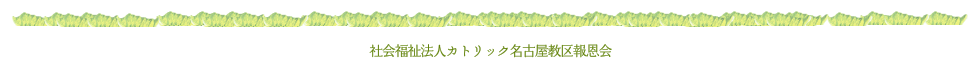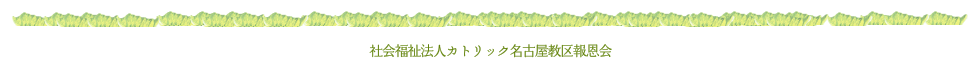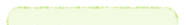 |
児童養護施設
『麦の穂学園』
|
 |
|
|
実習生受け入れについて
養育方針 「子どもが大切にされたと感じる養育をめざす」
◇実習生の受け入れ方針
社会福祉施設の養育の担い手の育成は、私たちの重要な役割であると考えています。次の世代を担う福祉の人材を育成するため、積極的に実習生を受け入れていきます。
また、社会とのパイプにもなる実習生を受け入れることで開かれた養育を目指し、社会的養護についてよき理解者を得ることも大切にしていきます。
◇実習のねらい
- 児童福祉施設の実習を通して、社会的養護の子どもたちの生活の現状や感情、自立にむけた取り組みを知る。
- 保育士・指導員をはじめ、家庭支援・栄養士・心理士等の他職種との連携を知ることにより、子どもたちの支援が包括的に行われていることを学ぶ。
- 地域と施設の連携や協力体制について理解を深める。
- 養育の担い手としての特性・資質について触れ、自己を振り返る機会とする。
◇実習のプログラム
基本的に、現場実習を通して保育士・指導員と共に子どもの関わり・生活援助の実習を行います。現場実習では、中小のグループの生活実習・調理実習を行います。その中で、こんな時にはどうしたらいいのだろうという疑問点や、子どもとの関係づくりの変化など様々な気付きが生じてきますので、充分に実習の振り返りができる時間を設け、実習の取り組みがステップアップしていけるようにしていきます。
◇実習に入るにあたって【実習の心得】
- 子どもにも職員にも、笑顔で心地よい挨拶を心掛けましょう。
- 時間厳守、常に 5 分前行動を心掛けてください。
- 服装は清潔感があり活動しやすく、下着が見えたり透けたりしないものにしてください。髪型も実習にふさわしい髪形にしてください。マニュキア、ピアス、指輪、つけまつ毛などはしないこと。爪を短く切ってきてください。
- 子どもたちの対応で判断に困った時は担当職員に確認し、適切な指示を仰いでください。
- 子どもたちは実習生の方の動きをよく見ています。実習は、観察実習ではなく参加実習につとめ、積極的に子どもと一緒に取り組もうという姿勢でのぞんでください。
- 実習ノートは担当職員から受けた助言等も含め、実習の目標と振り返りの視点を持って記入しましょう。客観的に自己を振り返ってください。
- 子どもと個人的なやりとり(携帯や手紙や金品等)はしないようにしてください。
- 元気な笑顔で実習が行えるように、十分睡眠時間を取り、体調を整えましょう。
- 大人から子どもへの感染を避けるため、体調不良は我慢せずに申し出るようにしてください。
- 実習時間中は、携帯電話の所持または使用することはできません。
- 実習中に知り得た子どもの情報については、個人情報保護の観点から実習学習の場以外で外部に漏らすことがないようにしてください。SNS などへの書き込みは絶対にしないでください。
- 子どもの写真はとらないでください。
- 宿舎および敷地内での喫煙は禁止です。
- 実習は公共交通機関を利用し、初日は所定時間内までに来園してください。前泊が必要な場合は、事前に申し出てください。
◇事前準備
- B4の大きさの画用紙に顔写真の入った「自己PR」を準備してください。実習期間中、食堂に掲示します。まず自分自身を知ってもらうことは、子どもたちとの関係づくりではとても重要です。子どもたちが実習生の方に興味を持ち、話してみたいと思うような「自己PR」を期待しています。
- 事前オリエンテーションの時に詳細資料【実習の流れ、子どもと関わるときの配慮事項等】をお渡ししますので、よく読んできてください。
- 「実習に向けての事前学習」のレポートを書いて、実習初日に提出してください。
◇宿泊について
- 保育実習は、宿泊実習を基本としています。
- 宿泊室に備えてあるもの
冷暖房完備 浴室 トイレ ミニキッチン 寝具 洗濯機 冷蔵庫 電子レンジ 湯沸かしポット ドライヤー 掃除用の洗剤 ごみ袋 など…
- 宿泊室(ゲストハウス)は、常に整理整頓、掃除、節電を心掛けてください。
- 宿泊室(ゲストハウス)の使用については、事前オリエンテーションで説明します。
- 実習中の個人的な外出はできません。(休日以外)必要なものは準備をしてきてください。
- 貴重品(お金等)は紛失を防ぐために必ず宿泊場所の施錠を行ってください。
- 実習最終日は、15:00頃に利用料(食費・宿泊費)の支払いを事務所で行ってください。
- 食費(1食300円×食数) 宿泊費(1泊1000円) 本代(児童福祉ぎふ 1000円)
◇持ち物について
- 実習関係書類(実習ノート、出勤簿等)
- 細菌検査表
- 行動記録表
- 認印、筆記用具、メモ帳、レポート用紙
- 健康保険証
- 洗面入浴用具、タオル、洗濯用洗剤
- エプロン、三角巾(バンダナ)
- 名札、スリッパ
- 帽子、運動靴
- 休憩中の飲み物、軽食
- 食費(1食300円×食数)
- 宿泊費(1泊1000円)
- 本代(児童福祉ぎふ 1000 円)
- その他 季節によって必要なものなどは、事前オリエンテーションで説明します。
◇実習の流れ
- 実習初日は公共交通機関を利用し、所定の時間までに来てください。1時間前くらいより宿泊場所に入室できます。
- 受け入れでは、食事表の記入、提出物の確認、宿泊場所の確認をします。実習ローテーション表をお渡しします。
- 実習場所は、子どもの生活グループ、炊事、小規模グループ等をローテーションでおこないます。
- 実習ノートは、翌朝、学生の一人がとりまとめて事務所に提出してください。
- 実習時間
<通常日程>
- 子どものいる時間を基本に、1日8時間前後の実習をおこないます。「振り返り」時間では、気付き・自分の課題・成長点等、自分の振り返りをし、次の実習の向上に取り組みます。
<最終日日程>
- その日の担当場所にて実習後、その日の実習ノートや「実習を終えて」のレポートを記入・提出、宿泊場所の掃除、振り返り、利用料の支払い等を行う。
- *寝具のシーツ類は、起床後に洗濯→たたみをし、初日の状態に戻してください。
- *ごみは、帰る際に子ども用玄関まで持ってきてください。
- 実習の休日に外出する場合は、事前に実習担当職員に伝え、午後8時迄に帰園してください。
|